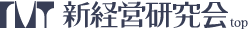- 2007-04-06 (金) 2:24
- 異業種・独自企業研究会
 2007年3月28日、私たちは、越前和紙の中でも最高峰といわれる生漉奉書紙(きずきほうしょし/100%楮で漉き上げる厚手の和紙)で国の重要無形文化財保持者(人間国宝)の認定を受けている九代 岩野市兵衛氏を、その工房に訪ねさせて戴いた。 その詳細は、この会のコーディネーターをお願いしている相馬和彦氏のレポートに譲り、私はその付記として、おこがましいことではあるけれども、若干の所感を述べさせて戴くことにしたい。 九代 岩野市兵衛氏の御尊父に当る先代は、水上勉の名作「弥陀の舞」のモデル、主人公の弥平その人である。生漉奉書紙漉き一筋に生きて、1968年、国の重要無形文化財保持者に認定され、越前の名紙匠といわれた。常に最高品質の奉書紙つくりに精魂を傾け、摺師の腕前にも大いによる処であるが、木版画で400回もの摺りに耐えて紙の伸縮によるずれもなく、年とともに色彩が冴え、強靱で、歴史的にも最高品質といわれる越前奉書紙をつくり上げた人である。ピカソや横山大観が愛用した和紙も、この八代 岩野市兵衛氏の制作によるものであった。
2007年3月28日、私たちは、越前和紙の中でも最高峰といわれる生漉奉書紙(きずきほうしょし/100%楮で漉き上げる厚手の和紙)で国の重要無形文化財保持者(人間国宝)の認定を受けている九代 岩野市兵衛氏を、その工房に訪ねさせて戴いた。 その詳細は、この会のコーディネーターをお願いしている相馬和彦氏のレポートに譲り、私はその付記として、おこがましいことではあるけれども、若干の所感を述べさせて戴くことにしたい。 九代 岩野市兵衛氏の御尊父に当る先代は、水上勉の名作「弥陀の舞」のモデル、主人公の弥平その人である。生漉奉書紙漉き一筋に生きて、1968年、国の重要無形文化財保持者に認定され、越前の名紙匠といわれた。常に最高品質の奉書紙つくりに精魂を傾け、摺師の腕前にも大いによる処であるが、木版画で400回もの摺りに耐えて紙の伸縮によるずれもなく、年とともに色彩が冴え、強靱で、歴史的にも最高品質といわれる越前奉書紙をつくり上げた人である。ピカソや横山大観が愛用した和紙も、この八代 岩野市兵衛氏の制作によるものであった。


米原駅で新幹線を北陸本線特急しらさぎに乗り継ぎ、北陸トンネルを抜けると、奈良時代に国府が置かれ、平安時代には紫式部が少女時代を過ごしたという‘武生’の駅に着く。そこから車で十数分、のどかな田園を走ると、越前五箇と呼ばれる、わが国最高品質を誇る「越前和紙」の産地である。その大滝町という所に、九代 岩野市兵衛氏の工房がある。
記録に残る最古の越前和紙は、正倉院に保管されている天平2年(730年)の越前国大税帳断簡(切れ切れに残っている紙片)だそうで、その技術は既に極めて高度なものであるという。以来、越前和紙は、千数百年に亘り、しかも越前五箇と呼ばれるこの地で、先人の技術を継承、常に向上・革新しながら漉かれつづけられて来た。
岩野市兵衛氏によると、越前和紙はとくに奉書紙を源流に、時代の要求に応じて、檀紙、鳥の子、色付奉書紙、書画用紙、襖紙など、様々な和紙が生み出され、常に最高の品質と品格を誇って来たという。
織田信長や豊臣秀吉の時代には別格の公用紙として取り扱われ、徳川幕府においても特別の格式を与えられていた。歌磨呂や広重、北斎など、江戸時代の初摺り高級浮世絵版画はもちろん越前奉書紙で摺られたものだし、明治に入っては、太政官札用紙は何とここ越前五箇ですべて漉かれた、ということである。
商品のライフサイクル、或いは、古今を問わず、企業、産業の栄枯盛衰の習いから見ても、幾ら常に最高級品を求めつづけて努力して来たとはいえ、実に千数百年もの長い間、終始、越前和紙が揺るがぬ王座を占めて来た事実、しかも、それはこの越前五箇という、極く限られた一地域においてつづいて来たという事実は、誠に驚嘆すべきことで、希有、奇跡とさえいえる。この秘密は、今後、真剣に研究されてよいことだと、つくづく実感した次第である。
 この越前和紙の長い歴史の中で、頑に守り伝えられて来たのは、「長い繊維を長いままに使う」、そして「自然のものは、自然の性質のままに使わせていただく」ということであったという。
この越前和紙の長い歴史の中で、頑に守り伝えられて来たのは、「長い繊維を長いままに使う」、そして「自然のものは、自然の性質のままに使わせていただく」ということであったという。
そのため、九代 岩野市兵衛氏の言葉によると、奉書紙制作のどの工程においても、酷寒、炎暑にかかわらず、自然の繊維が自然の性質を損なわず、むしろより発揮出来るように、文字通り精魂傾け、自然の命に手を添えるように、納得いくまで時間と手間ひまを掛るという。和紙づくりの殆どの工程は、傍目には実に地味な、現代においては考えられない程に根気を必要とする作業である。
岩野市兵衛氏の、紙を漉きながら口ずさむ紙漉き唄にうっとり心を奪われながら、改めて、本来ものづくりとか労働というものは、このように、今のわれわれには及びもつかないほど過酷で厳しいものがあったけど、そこには、また同時に、今日とは比較にならない程の充実感と喜びがあり、それは、今日よりも、もっともっと人間的な営みであったのだと、改めて深い感慨に耽った次第であった。思えば、昔は、どのような労働にも、そこには必ず唄がつきものであった。
閑話休題、アダチ版画研究所会長の安達以乍牟氏によると、生漉奉書紙のふっくらとした柔らかな肌合いは、女性の肌を連想させるという。そのため、歌麿などの大首絵など、浮世絵の色白美人の顔の多くは、奉書紙の地肌そのままを使うのだそうである。
また、越前生漉奉書紙で摺った浮世絵版画の発色は、他産地のものに比して格段に優れているという。
ここで特徴的なのは、浮世絵で使われる絵の具は紙の表面に留まらず、内部まで染み込み、絵に現れる色は絵の具本来の色ではなく、紙の繊維との融合によって生まれる色なのだそうである。
また、浮世絵では、歳月と共に絵の具は紙の中で更に落ち着き、作品が創作時よりも更に味わい深いものになっていくという。
しかも、優れた生漉奉書紙は、年とともに、それなりに年をとって行くという。それは、優れた生漉奉書紙がひとしく備える、品格とでもいうべきもので、その年のとり方は美しく、風格のあるもので、実に立派に年をとっていく。それは古陶磁器などにも通じるものがある。
その、先代同様、生漉奉書紙漉き一筋に生きて来た、生漉奉書紙の人間国宝 九代 岩野市兵衛氏ご自身の口から、「紙の王者は雁皮紙。気品がある」という言葉が出た時には、岩野市兵衛氏の微塵も驕りのない、余りに真摯で正直なお人柄を垣間見て驚いた。今度、じっくりと奉書紙と雁皮紙を手に取って観賞したいと思っている。
安達以乍牟氏によると、平安時代の、例えば『桂本』などの『万葉集写本』、或いは日本美術を代表する最も有名な絵巻の一つ、徳川家伝来の『国宝 源氏物語絵巻』などは、雁皮紙が用いられているという。ただし、浮世絵版画には、雁皮紙は硬すぎて向かないのだそうである。
ところで、心配なことがある。
それは、岩野市兵衛家でも、先先代の頃までは地元福井の楮を使っていたが、昭和の初め頃から入手困難となり、先代から石川県産の加賀楮を使うようになった。 この加賀楮は最高品質のものだったそうで、光沢があり、ふっくらとして、暖かみと気品ある風合いを出す楮だったという。しかし、その加賀楮も栽培者の後継不足で入手出来なくなり、今は茨木産の那須楮(別名 水戸楮)を使っているという。
この加賀楮は最高品質のものだったそうで、光沢があり、ふっくらとして、暖かみと気品ある風合いを出す楮だったという。しかし、その加賀楮も栽培者の後継不足で入手出来なくなり、今は茨木産の那須楮(別名 水戸楮)を使っているという。
しかし、最近、この那須楮の収穫量が極端に落ちているというのである。不作なのではない。金沢美術工芸大学の柳橋眞教授によると、出来は良くても、栽培農家が枝を切らないからなのだそうである(季刊和紙 NO.15 June 1998)。
楮は、1年生の枝しか使えない。2年生、3年生の枝では使いものにならないのである。今年、1年生の枝を切らないと、来年使える1年生の枝は極端に減少してしまう。
最近、タイ、ラオス、フィリピンなどからの安い楮の輸入が増大し、国内産の楮栽培が、今、深刻な危機を迎えている。
殆どの和紙生産者は、今日、原材料にそこまでの品質を求めない。今日の和紙需要の九割以上は、千年などという耐久年数はもちろん、微妙な肌触りや風合い、発色の違いは求めていない。バブル崩壊後、高価な国産原材料を使った高級品では、商売にならないのである。
実は、これほど常に本物の材料を求め、最高品質の生漉奉書紙つくりに精魂を傾けている岩野市兵衛氏も、灰煮(煮熟のこと/しゃくじゅく:楮皮を柔らかくし、灰汁抜きをするために煮る、和紙制作の初期工程)の灰はソーダ灰を使っている
- Newer: 学ぶ意欲と想像力/森 健一氏
- Older: 「越前和紙に学ぶ伝統の技と魂」生漉奉書紙 人間国宝 岩野市兵衞氏工房訪問