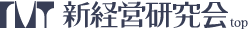- 2007-06-29 (金) 21:56
- イノベーションフォーラム21
 と き:2007年6月22日(金)
と き:2007年6月22日(金)
訪問 先:キッコーマン株式会社 本社・野田工場
講 師:代表取締役会長 CEO 茂木友三郎氏
コーディネーター: 相馬和彦氏(元帝人(株)取締役 研究部門長)
「異業種・独自企業研究会」の2007年度 第5回例会は、千葉県野田市にあるキッコーマン(㈱)の本社・野田工場で開催された。本社・野田工場は東武野田線の野田市駅から数分の距離にあり、駅を出るとすぐに醤油醸造独特の匂いに包まれ、野田市が醤油製造の町であることが実感された。
 まず「もの知りしょうゆ館」にて高松洋 取締役常務執行役員の出迎えをいただき、日本における醤油とキッコーマンの歴史についてお話を伺った。
まず「もの知りしょうゆ館」にて高松洋 取締役常務執行役員の出迎えをいただき、日本における醤油とキッコーマンの歴史についてお話を伺った。
日本における醤油の先祖は、紀元前七世紀から魚介・鳥獣の肉や内臓、野菜などを塩漬けにして熟成した「ひしお」である。中国から618年に「唐びしお」が、その後朝鮮半島からも類似のものが伝来したが、鎌倉時代になると「溜しょうゆ」のようなものが見つかっている。今日のような醤油が作られるようになったのは戦国時代からであり、その頃から漸く庶民の口にも入るようになった、という。
国内の醤油消費は人口と嗜好の変化により、工場数は1955年の6,000社から2004年の1,429社に、生産量も1974年の120万Klが、2005年には94万Klに減少し、世界の醤油生産量は1996年の統計によると、本醸造が260万Kl、中国式が610万Kl、混合80万Kl、非醤油(化学品)20万Klの合計970万Klであった、ということである。
その後工場見学に移り、先ず、近代的な醸造プロセスを見学した。工場は古くからの伝統的な製造法を大規模な化学工場に移し変えたものであり、製品の生命を握るのはキッコーマンの所有する麹菌および味に影響する乳酸菌・酵母などの菌類であることは変わりがない。つづいて、伝統的な醸造法を古式通りに今に伝える「御用蔵」を見学したが、ここでは朱塗りの、伝統的な桶を用いる醸造法が維持されており、近代的な工程では製品完成まで六ヶ月かかるところ、一年間かけてじっくりと熟成されている。桶に住み着いた菌が利用され、完成品は宮内庁に納められて園遊会などで使用されているとのことであった。
工場見学の後、1999年に竣工された本社に移り、茂木友三郎代表取締役会長兼CEOから「創業90年・海外事業展開50年 世界の調味料を目指して」と題したご講演をいただいた。キッコーマンの創業時代から始まり、米国への進出、現地生産の展開、欧州・アジアへの国際化、今後の展開方針に至るまで、予定された1時間15分ぴったりのご講演中にデータや事実関係、その背後にある経営思想まで、全くメモを見ることも無くお話された。
現地生産の企画から実行までのすべての過程でリーダーシップを取られたとはいえ、異業種研究会25年の歴史でもこのような感動的なご講演は稀有なことであり、その卓越した記憶と決断、論理的・合理的な内容、経営者としての志の高さに一同強い感銘を受け、一流の経営者としてあるべき姿を垣間見させていただく思いであった。
17世紀以来、醤油は野田を本拠とした地場産業であった。野田で醤油が繁栄したのは、市場と原料の両面で立地上有利であったため、ということだ。
大消費地である江戸へは、江戸川を利用した船で大量輸送が出来た。また原料である大豆、小麦、食塩は近くで調達可能であった。
キッコーマンは、もともと1917年に、醤油醸造家7家、みりん1家の8家が合同で設立した野田醤油が基である。
巷間、合併企業というものは、普通はその当初において内紛が絶えず、なかなか経営が潤滑に運ばないといわれているが、幸か不幸か、当時は産業革命による工場近代化の時代であり、それに反対する組合が結成されてストライキを打ったため、創業家は結束してこれに当らなければならず、結果、揉め事を起こしている暇などなかったのだという。このストライキは280日間続き、後に日本三大ストライキの一つと言われたが、そのお蔭で経営者は団結し、また新設の第一工場の従業員が組合員でなかったこともあって、会社は持ちこたえた。
昭和も30年代になると国民の生活レベルも回復し、醤油消費量は人工の伸び程度に落ちた。
昭和35年に池田内閣が誕生して所得倍増方針を発表した。倍増と言えば、年率で7%以上の成長が必要となる。
キッコーマンは成長のための二つの方針を策定した。第一は醤油以外への多角化であり、もう一つは醤油の国際化である。
多角化では、デルモンテと結んだトマトジュース、ケチャップへの進出、ワイナリーの買収によるマンズワイン事業、利根コカコーラ、醤油副産物である酵素開発などである。
国際化では米国本土への進出を選択した。キッコーマンは戦前にも醤油の輸出や、韓国・中国・インドネシアなどでの生産を行っていたが、これはあくまで日系人が顧客であった。それを転換し、敢えて米国本土を選んだのである。それにはヒントがあった。戦後多くの米国人が日本に駐在したが、軍人以外の米国人が日本滞在中に醤油を使い始めたのを見て、米国本土でも売れるのではないかと考えたのである。1957年にスーパーに商品を並べて本格的なマーケティングを開始し、1975年には漸く黒字化した。進出当時の売上は全社の1%程度で赤字であったが、今では売上の約30%が海外(内米国約80%)、利益に至っては約50%が海外(内80%が米国)となり、海外事業はキッコーマンにはなくてはならない地歩を占めている。
 米国に進出した際には、販売会社を1957年にサンフランシスコに、翌年にはロスアンジェルスに設立してまず西海岸から広め、その後1961年にニューヨークに設立して東部へ、1965年にはシカゴに、続いてアトランタ、ダラスと続けて南部への拡大を図った。
米国に進出した際には、販売会社を1957年にサンフランシスコに、翌年にはロスアンジェルスに設立してまず西海岸から広め、その後1961年にニューヨークに設立して東部へ、1965年にはシカゴに、続いてアトランタ、ダラスと続けて南部への拡大を図った。
この時の販売活動としては、第一に醤油の味を覚えて貰うことを目的に、スーパーの店頭で醤油を使った肉料理のデモを行った。この時味見をしてくれた客の半数が実際に醤油を購入して呉れるのを見て手ごたえを感じた。この当時コロンビア大学のMBAに留学していた会長は、店頭でのデモ販売をご自身で体験している。
第二は醤油の使い方を教えることで、サンフランシスコにテストキッチンを開設し、そこで工夫した様々な米国人向けのレシピを新聞の料理欄に出して貰ったり、料理本を出版した。
第三には丁度その頃大統領選挙があって選挙速報がラジオで放送されたが、北カリフォルニアの速報番組を買ってキッコーマンの名前を宣伝した。これがバイヤーにインパクトを与え、その後役立った。
米国の拡販で利用したのがブローカーであった。彼らは在庫を持たず、小売店を開拓してコミッションを受け取る。流通では日米に大きな差がある。日本はタテ社会で上下関係のある人間関係を重視し、既得権を尊重するが、米国ではヨコ社会でメーカーから流通、小売まで同等であり、ルール、機能を重視する。米国の醤油市場では最初からNo.1であったのではなく、徐々に伸びることによって結果的に市場の55%を占めてNo.1となった。No.2、No.3は米国化学醤油メーカーであり、醸造醤油と化学醤油は料理への添加物として味覚上あまり差が出ないが、テリヤキソースとして使うとはっきりと品質の差が出た。
米国内の販売は当初赤字であったため、この時期に現地生産の必要性が認識されるようになった。
米国留学から帰国した茂木会長は、この段階から企画および現地生産業務を担当してリーダーシップを発揮したため、詳細に渡る内容をお聞きすることが出来た。
当時米国で現地生産している日本企業はなかったが、同じ時期にソニー、YKKが現地生産のための調査を行っていたことが後になって判明した。現地生産の利点としては、①海上輸送費がゼロ、②輸入関税がゼロ、③原料に米国産品を使用するので、輸送費と在庫がダウンする、などがあるが、逆に現地生産のデメリットとして、①陸上輸送費が掛かる。これは大量輸送でカバーする、②設備が特注となるため、投資額が増えることなどがある。
現地生産の場所としては、ウインスコンシン州のウオルワースを選んだ。その理由は、①全国向け輸送に便利、②原料入手が容易、③労働者の質が高く勤勉、④地域社会が良く、犯罪が少ないことであった。この時農地を工場用地に転用することへの反発から、思いがけなく現地で反対運動が起こった。 工場から公害は出さないこと、農業と共存共栄することが可能であると主張し、二ヶ月かけて説得に成功した。現地化では現地との共存共栄が必要であることを痛感し、これを教訓として現地化方針を策定・実行した。①共存共栄のために経営を現地化する。同じ条件ならば、取引先として日本メーカーではなく、近くの米国企業を優先する。②現地人を採用する、③現地の活動に参加し、日本人だけ固まって住まないなど、現地社会に融け込む。これが成功し、過去30年間米国では二ケタ成長を遂げ、カリフォルニアに第二工場を建設するに至った。
工場から公害は出さないこと、農業と共存共栄することが可能であると主張し、二ヶ月かけて説得に成功した。現地化では現地との共存共栄が必要であることを痛感し、これを教訓として現地化方針を策定・実行した。①共存共栄のために経営を現地化する。同じ条件ならば、取引先として日本メーカーではなく、近くの米国企業を優先する。②現地人を採用する、③現地の活動に参加し、日本人だけ固まって住まないなど、現地社会に融け込む。これが成功し、過去30年間米国では二ケタ成長を遂げ、カリフォルニアに第二工場を建設するに至った。
欧州では1979年にドイツで販売を開始し、米国で確立したビジネスモデルを踏襲した。米国と少々異なるのは、醤油の販売促進のために鉄板焼きレストランを展開したこと。現在では役割が終わったため、2軒に減らしている。また国ごとに異なる好みを反映させるため、各国の料理学校と提携してレシピの開発に努めている。販売はディストリビューターを経由しているため、販売コストは米国よりは高くなる。市場立地上便利なため、工場はオランダに設立したが、欧州では毎年15%の成長を遂げている。
オーストラリアでは米国に類似したセールス展開を行っている。台湾では合弁で進出し、合弁相手はNo.4であったが、合弁後にはNo.1となった。この合弁で中国へも進出した。
これからの成長と多角化のため、米国では健康食品会社を買収して数年前から豆乳に進出した。付加価値の高い有機醤油もこれから有望である。欧州では後10年は今のままで成長が可能であろう。中国や東南アジアでは、現地の醤油が安く、キッコーマンの醤油では5倍するが、10年~15年すれば購買力がアップすると長期的に見ている。同時に中国やインドなどの高成長国向けの商品開発のため、2005年にはシンガポールに開発拠点を設置した。これらの更に先の市場は南米であろう。何しろ肉と醤油の相性が良いことは、18世紀から欧州では知られたことであった。
海外進出と現地化を、日本企業のパイオニアとして陣頭指揮で推進してきた茂木会長のお話には、本格的なグローバル化の真只中にいる我々には数え切れない教訓を見出すことが出来た。更には、食文化のような最も保守的な文化さえ、挑戦によって変革することが可能であるという勇気もいただくことが出来、まことに充実した訪問となった。 (文責 相馬和彦)