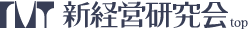Home > アーカイブ > 2008-09
2008-09
キヤノンのものづくり戦略
- 2008-09-12 (金)
- イノベーションフォーラム21
と き :2008年8月21日
会 場 :森戸記念館
ご講演 :キヤノン(株) 常務取締役 本田晴久氏
コーディネーター:LCA大学院大学 副学長 森谷正規氏
「21世紀フォーラム」2008年度前期の最終回は、キヤノンの本田晴久常務取締役生産技術本部長から、キヤノンのものづくり戦略のお話をいただいた。まずは会社紹介だが、創業以来のDNAから始まった。それは「技術重視」、「進取の気象」、「人間尊重主義」の三つであり、人間尊重の中には「三自の精神」つまり、自発、自治、自覚がある。2007年の業績では、売上高が4兆4813億円、純利益が4883億円であり、利益率は10、9%になる。最近になってようやく、低収益が一般である日本企業の間に利益率が10%を超える企業がかなり現れてきたが、キヤノンはその代表格である。キヤノンは特許を非常に多く登録していることで有名だが、過去10年間の米国特許累積登録では、IBMに続いて2位である。地域別売上高では、国内は21%で8割は海外であり、まさしくグローバル企業である。
次いで、キヤノンの長期経営計画・構想の変遷についての話があったが、新しいものは「グローバル優良企業構想」であり、「全体最適の追求」と「利益優先主義への転換」が意識改革の目標として挙げられている。利益優先のための生産革新では、セル生産を広く導入してコンベアを全廃しており、それは20kmに達し、また外部倉庫の返却は15万平方mにもなっている。「設備のムダをなくす」ことを強調されたが、これは目新しいことである。工場に立派な設備を持つのは、とかく自慢になるのだが、そこにムダがないか徹底的に探し出して、設備投資額もスペースも減らしてムダをなくすように最大の努力をするのである。
また、セル生産を通して「ものづくりは人づくり」であると気づいて、「マイスター制度」を設けた。優れた技能を持つ多能工者を認定し表彰するのである。最初から最後まで自律して仕事をこなす作業者を多能工者とするのであり、セル生産に必要である。高度なカラー複写機を一人で組み立てる作業者がいて、それはマイスターのS級、最高位としている。
いま目指している開発生産革新に話が入ったが、それは「内製化と統合的ものづくり」である。キヤノンは、いま改めて内製化の拡大を目指すという。キーデバイス・キーコンポーネントを自社で開発・生産するとともに、ユニット部品や基盤実装、さらに製造装置、レンズや部品を成型する金型などの内製化を進めるのである。それは、より独創的な製品を創出することとコストダウンを両立させるためである。製造装置や金型まで、内製化の幅がとても広い。これは商品開発のスピードアップやリードタイムの短縮にもなり、内製化こそが競争力の源泉であるとする。製造装置では自動組み立て装置を開発するが、専門企業を買収しており、金型も金型メーカーを買収して、グループ企業化している。
キヤノンは、自動化生産に積極的である。御手洗富士夫会長が、日本企業の国際競争力維持の一つの道として、完全な自動化生産を挙げている。いまそのための組み立てロボットを内製化しようと自社で開発している。
「統合的ものづくり」は、二つの事例を基にして話された。一つは、トナーカートリッジである。これはキヤノンが卓上複写機の心臓部として開発した独自の部品であり、感光ドラムとトナーを含む高度な部品である。その構造と開発の経緯から話が始まったが、高度な原材料生産、自動化生産、回収・リサイクルまで統合して行っている。これが、技術で独走し、また高利益を上げている源泉であることが良く分かった。
二つ目の事例は、DOEと超精密加工技術である。DOEは、回折光学素子のことであり、超高級レンズに用いられて、レンズ性能を向上し、小型化、軽量化を可能にする。基板となるガラスレンズの間に非常に複雑な形状のプラスチックを挟むのであり、その成型の金型に、世界最高性能の超精密加工装置を用いる。光学設計、素子設計から始まって、金型と加工装置、材料、成型、さらに形状測定機まですべて自社内で技術開発し製作したのである。
国際競争がいっそう厳しくなる中で、キヤノンの内製化を基にした統合的なものづくりは、真に良い製品をコストを上げずに作って国際競争に打ち勝つ有力な方向であることが良く分かった。
(2008年9月 森谷正規)
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
画期的光学用高機能樹脂ZEONEXの開発、ブレークスルーへの軌跡
- 2008-09-08 (月)
- イノベーションフォーラム21
と き :2008年7月28日
会 場 :アイビーホール青学会館
ご講演 :日本ゼオン(株) 代表取締役専務 夏梅伊男氏
コーディネーター:LCA大学院大学 副学長 森谷正規氏
21世紀フォーラム2008年度前期の第5回は、日本ゼオン代表取締役専務である夏梅伊男さんの「画期的光学用高機能樹脂ZEONEXの開発、そのブレークスルーへの軌跡」であった。ファインケミカルズとも言われて早くから大きな期待が持たれた高機能樹脂は、多くの分野で実用化が進んでいるが、その最も有力なものの一つが光学用透明材料であり、その中核がレンズである。中でも日本ゼオンが開発したZEONEXは、優れた光学特性を持ちプラスチックレンズのトップを走っていて、カメラ付き携帯電話機のレンズでの世界シェアが90%に達している。そのZEONEXのさまざまな面での独創的な開発のお話をお伺いすることができた。
ZEONEXは1991年に市販されたが、その開発は当初はアングラであり、1987年から本格化した。そのきっかけは、ある電機メーカーの研究所から次世代の記録メディアとして期待された光磁気ディスクにゼオンの透明プラスティック材料が使えないかとの問い合わせがあったことだ。光磁気ディスクには、先行していた他社製品が採用され、またこのディスク自体が伸びず、成功にはいたらなかった。だが夏梅さんは、光学透明材料に大きな可能性があることを知った。
当時は、ポリカーボネイトとメタクリル樹脂が光学用に利用されていたが、ガラスと比較して吸湿性が高い、複屈折率が高い(歪みを生じる)、耐熱性に劣るなどの問題点があった。そこで日本ゼオンは、シクロオレフィンポリマー(COP)に目を付けて開発を始めた。これは光学材料に要求される諸性能のすべてを満たす優れた特性を持っていたのだ。COPはこれまで絶縁材として研究を行っており、基本となる特許を保有していた。
夏梅さんが中心になって開発したのだが、新分野を開くためにはともかく他社に先行しなければならないとして、並のやりかたではなく、思い切ったことをいくつもやった。一つは諸性能を実現するための研究を続けるとともに、同時に開発も急いだことだ、基礎研究と製品化への開発の同期化であり、スピードを重視した。こうしてまったくの新規材料ながら、わずか3年半でZEONEXとして市販に漕ぎ着けたのである。
もう一つは、いかにして商品として成功させるかの方策を懸命に考えたことだ。ガラスに代わるプラスチック光学材料として新分野を開拓しなければならず、これまで馴染みのない顧客にいかに受け入れられるかが基本的な大問題であった。そこで、多くの顧客に早くサンプルを提供して、顧客からのさまざまな情報を得て、開発にフィードバックさせることにした。サンプルを出せば情報が競合他社に伝わる恐れがあるのだが、それは意に介せず、顧客の意向をとらえて開発に活かすことに努めたのだ。
さらに、速やかに製品を提供しなければならないと、いきなり1000トンの大型プラントを建設した。これは異例のことである。当初は小型のプラントで作り、市場が伸びるとともに生産設備を拡大するのが一般だが、それでは間に合わないとして、市場が未成熟の状態で本格的な生産に入ることを決断して、顧客に製品提供の確約をしたのである。経営陣の中ではいきなりの大型プラントに反対意見が強かったが、夏梅さんは必要性を強く主張して、建設を実現させた。
こうしてZEONEXは、短期間で商業化を開始することができたが、レンズのプラステイック化は大きな流れとなって、CD用などから需要は急速に伸びていった。さらにDVDからブルーレーザー用と広がってきて、携帯電話機用が急進して売上高はグングンと拡大していった。初期の成功ばかりではなく、いまに続く事業発展のためにも、いくつかのユニークな戦略を取ってきた。それらがまさしく独創的とも言えるものである。
その一つは、知的財産活動が主導するR&Dである。つまり、特許を生み出すためのR&Dであり、このようなニッチマーケットでは、すべてを特許で抑えて、後発の企業が参入できないように入り口を抑えるのが必須と考えたのである。
また一つは、部材メーカーであるが、デジタルの時代の展開を読んで、適用する情報機器についてのロードマップを先取りして、新たな方向を探ることである。機器メーカーは当然やることだが、部材メーカーとしてもそれに力を注ぐのだ。そして、ロードマップをもとに機器メーカーに提案マーケティングを行う。ともかく、市場のニーズを探ることに全力を注ぐのである。それは、ZEONEXの初期に必要に迫られてやって、見事に成功したので、それが習い性となっているようだ。市場からスタートするという技術開発に徹しているのが、日本ゼオンの光学用プラスティックである。
(2008年9月 森谷正規)
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
日本のロボット研究、その未来の可能性
- 2008-09-05 (金)
- イノベーションフォーラム21
と き :2008年6月13日
会 場 :森戸記念館
ご講演 :早稲田大学 理工学術院 教授 高西淳夫氏
コーディネーター:LCA大学院大学 副学長 森谷正規氏
「21世紀フォーラム」2008年度前期の第4回は、「日本のロボット研究、その未来の可能性」であり、早稲田大学を訪問して教授の高西敦夫さんにお話いただき、数多くのユニークなロボットを見せていただいた。早稲田大学は、歩行ロボットの開発で著名な故加藤一郎教授以来、ロボットの研究開発に非常に大きな実績を持っているが、高西さんはいまその中心にある。
ロボットの研究開発は、10年ほど前から二足歩行の実現から始まって人間に近づけるヒューマノイド研究の分野が大きく進んでいるが、早稲田大学は2000年にヒューマノイド研究所を設立して、高西さんがいま所長として研究をリードしている。
まずは本部で高西さんの総括的なお話をいただいたが、それは日本人のロボットの受け止め方から始まった。日本では古くからカラクリ人形などが作られていて、ロボットを身近なものとして好んできた歴史があるが、さらに針塚での針供養の例を出して、針のようなごく小さなモノにも愛着を感じるのが日本人であるという説を披露して、印象的であった。
早稲田大学での研究の紹介に移ったが、ヒューマノイドとして研究に力を注いでいる一つが、“情”である。感情表出をロボットでいかに実現するか、そのモデルを構築して研究している。実物ではなく映像で見せていただいたのだが、まゆ、目、口などを動かして、喜び、怒り、驚き、悲しみ、嫌悪などの表情を表す情動表出ヒューマノイドロボットを開発していて、その顔の動きを見ることができた。このロボットは視覚、触覚、聴覚、嗅覚の四つの感覚を持っていて反応するのだが、そのオーバーな動きが面白かった。その開発目標は、心身統合メカニズムの解明である。メカニカルな動きと心理を結び付けようというものだ。
昔からの二足歩行ロボットもより高度なものを開発しているが、ホンダのASIMOとの違いが良く分かった。ASIMOを始めとして二足歩行ロボットは、膝を曲げて、腰を落として歩いている。少々、格好が悪い。だが、早稲田のWABIAN-2は、腰をあまり落とさずにスッキリと歩く。高西さんの説明で、その違いが分かったのだが、ASIMOは、歩行の安定性を保つために、膝を伸ばし切らないようにして、不測の事態に備えている。したがって、通常は膝を曲げて歩く。一方、WABIANは、腰の部分にも自由度を持たせる仕組みを組み込んでいる。したがって、膝を伸ばして歩いても安定性が保たれるのである。
研究室では、WABIAN-2に加えて2本足の人体移動ロボットを見せていただいた。人を乗せて動くロボットだが、運輸、医療、福祉、娯楽などでの利用を目指している。片足が二本で構成された前後に長い足を持っているので、二足でも安定性が大きい。凹凸のある路面、多少傾斜した路面でも歩くことができて、体重60キロの人を乗せることができる。公道での実験も行っているが、さて、いかに実用化に進めるのか。商品としては、まだ大きくて不格好である。
ロボットには、非常に多くの多彩な実用可能性があるのだが、早稲田大学は、メディカルロボットの開発にも力を注いでいて、それは東京女子医大との共同研究であり、共同で建設した新しいビルの中に研究室がある。そこも訪ねる忙しい会であったが、たまたまこの共同研究ビルの建設に力を注いだ研究者がいて、その意義の説明を受けた。広い跡地があって、早稲田大学と東京女子医科大学が共同で購入して研究設備を作ることになったのだが、それは別個のビルとして計画された。だが、共同研究であるからには、一つのビルにすべきとの強い主張が出た。しかし、文部科学省は、前例がないと渋った。それを強く説得して、建設に漕ぎ着けたという。
ここには、脳手術のためのマニピュレータ、穿刺手術用知的マニピュレータなどの手術支援ロボットなど精緻なロボットの研究開発があり、また歩行支援ロボットなど実用的なロボットの開発も行われている。どれも近い将来の実用化を目指した開発である。
ロボットの研究開発は、実に幅広いものであることが良く分かった一日であった。大学の役割は、遠い将来の実用化を目指した基礎的な研究から、特殊な分野であり企業がなかなか手を出しにくい分野など、幅広く研究開発することであり、企業は大学と組んで開発するのが有力な方向であると実感できた。
(2008年8月 森谷正規)
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
最先端の脳神経科学から食を解き明かす
- 2008-09-03 (水)
- イノベーションフォーラム21
と き :2008年4月22日
会 場 :森戸記念館
ご講演 :味の素(株)ライフサイエンス研究所 上席理事 鳥居邦夫氏
コーディネーター:LCA大学院大学 副学長 森谷正規氏
「21世紀フォーラム」2008年度前期の第2回は、味の素株式会社のライフサイエンス研究所上席理事である鳥居邦夫さんから「最先端の脳神経科学から食を解き明かす」と題するお話をいただいた。鳥居さんは、このフォーラムにしばしば聴講に来られるお馴染みである。
お話は、鳥居さんの味の素の入社時から始まった。当時、味の素の成分であるグルタミン酸が、脳に悪影響を及ぼすという論が世に出て、自分はそれに反論する研究をするから採用してくれと申し出たとの面白いやりとりがまず紹介された。採用されたただちに研究した結果、マウスには影響があるが、人間にはまったくないという結論を出して、米国のFDAに認めて貰ったとのことであった。鳥居さんの話ぶりはとても威勢が良く、しばしば笑いを誘う楽しい話が、自身のエピソードとともに始まる。
話は、人類の発展の歴史から説くものであり、原人はアフリカから出て、世界に広まったが、なぜ、白人、東洋人、黒人が生まれたのか、食糧生産がいかに文明を生んだのか、産業革命がなぜ生まれたのかなどであり、それぞれに食糧が密接にからんでいることを示した。
次いで、食事についてのさまざまな話題が次々に、速射砲のように飛び出した。なかでも、高齢化の時代の重大な問題として、老齢になって食べたものの嚥下ができなくなると、胃に管で食物を入れて栄養を補っても、身体は一気に弱ってしまうという話が頭に残り、美味しく食べることの重要性を思い知らされた。
味覚と栄養については体系的な話があり、脳が食べてもいいとする情報を出すのに、味覚は深くかかわっていて、それが狂うと、食事、栄養のバランスがおかしくなって、肥満、虫歯、糖尿病、高血圧症などの病気の原因になるのであり、味覚は健康の維持にも非常に重要であると知らされた。
次いで、その味覚についての詳しい話がある。味覚の中身としてこれまで、「甘い」、「酸っぱい」、「塩辛い」、「苦い」の四つがあったが、そこに「うま味」が加わった。これは「umami」として国際的に使われ、学術用語にもなっている。日本語がそのまま外国語の一つとして使われている言葉はいくつかあるが、umamiはその一つであり、日本がいわば、うま味先進国であると言えるのだ。なお、からしなどの「辛味」は、味覚ではなく、刺激であるとのことだ。
そのうま味を育んできた日本の歴史が語られた。大化改新で税を取るようになり、それは米だが、米が取れない地域は、あわびなど乾物で税を納める。それを得た公御は、湯で戻して、野菜を煮るが、その乾物にうま味がたっぷり入っていて、美味しいのである。
やがて、「ひしお」が発達した。発酵させてつくるのだが、野菜を原料にする「くさびしお」が漬物であり、魚を原料にする「ししびしお」が調味料になり、穀物を原料にする「こくびしお」が味噌になった。
日本において早くからうま味が発達していて、それはまず貴族文化として生まれ、やがて庶民に広がったのである。
そして明治になって、池田菊苗博士が、1908年にうま味の成分としてグルタミン酸を発見する。それが味の素の出発である。今年はちょうど100周年であり、味の素は記念のプロジェクトを計画している。グルタミン酸は、味の素が積極的に世界に広げたことによって、いまでは、156カ国に広がり、年間200万トンも生産されている。
いよいよ味覚と脳の話に展開するが、舌には1万2千個の味蕾があって、味覚神経を通して脳に伝えられる。味蕾は胎児のころから生まれていて、羊水はコンソメの味であり、したがってコンソメは美味しく感じるのだそうである。
味覚、うま味と身体との関係が、豊富な実験データ、グラフで示される。粘液や膵液の分泌にうま味が深く関係している、うま味の物質がないと脳は認識できない、飽満感もうま味に深く関係している、コンソメ、ホンダシなどを摂取すると身体が暖まった感が出るが、それは基礎代謝が良くなるからであり、肥満防止に役立つなどと、興味がある話が次々に出てきた。
うま味が 健康にとって非常に重要であることが良く分かった。とくにいま重大な問題になっている肥満に深くかかわっている。
その後、意見交換、質疑応答が活発であった。面白かったのは、英国の食事は不味いという話から、国による味覚の違いに話が展開したが、味蕾の人種による違いはなく、脳での情報処理の問題であり、味に関心がないと、その面で遅れがあるのかもしれないという結論であった。
(2008年8月 森谷正規)
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
Home > アーカイブ > 2008-09