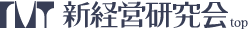- 2008-04-10 (木) 21:33
- 異業種・独自企業研究会
と き : 2008年4月4日
ご 講 演 : (株)瓦宇工業所 代表取締役会長 小林章男氏
訪 問 先 : 瓦宇工業所 針工場
コーディネーター: 相馬和彦氏(元帝人(株)取締役 研究部門長)
 2008年度(前期)「異業種・独自企業研究会」の第2回は、4月4日に瓦宇工業所の針工場を訪問し、選定保存技術保持者に指定され、日本でただ一人「鬼師」の称号を有する小林章男会長から、古代の瓦製造技術に関する知見をお聞きした。また静岡大学の志村史夫教授からは、古代瓦製造技術と現代半導体技術の関係についての研究成果も併せて伺うことが出来た。
2008年度(前期)「異業種・独自企業研究会」の第2回は、4月4日に瓦宇工業所の針工場を訪問し、選定保存技術保持者に指定され、日本でただ一人「鬼師」の称号を有する小林章男会長から、古代の瓦製造技術に関する知見をお聞きした。また静岡大学の志村史夫教授からは、古代瓦製造技術と現代半導体技術の関係についての研究成果も併せて伺うことが出来た。
以前の工場は奈良市内の中心部にあったが、最近郊外の針に工場移転したばかりである。新工場の稼動と蒐集した古代瓦や道具類の整理で大変ご多忙な中で、今回研究会の訪問を受け入れていただいた。古代瓦の整理と陳列はかなり済んでおり、古代瓦の陳列室を講演会場としたため、実物を目の前にしながらの講演は雰囲気満点であるばかりでなく、馴染みの薄い古代瓦について具体的な理解が得やすかった。貴重な瓦製造用の道具類については残念ながら整理が未だ済んでいなかったため、今回は拝見することが出来なかった。
講演に先立ってまず工場を見学した。乾燥工程では、成型した瓦は一週間ほど風を送って予備乾燥し、次に二週間ほど本乾燥する。予備乾燥するのは、次の本乾燥工程でひび割れするのを防ぐため。本乾燥室は焼成炉の真上に位置し、炉で暖まった空気が熱源として利用されている。乾燥された瓦は白色をしていて意外な感じがしたが、焼成炉で焼いた時にカーボンが付着して黒色に変化する。また土の組成やカーボンの有無によっても色は変化し、沖縄や東南アジアの瓦は赤茶色をしている。
瓦宇工業所では原料の土は奈良産のものを使用しているが、土置き場は未だ整備されていない。原料土は真空混練機で良く混ぜながら空気を抜き、水分量が21%になるように調整する。混練機から押し出されてきた板状の粘土を金属の刃で切断する。鎌倉時代の粘土は水分量が33%あったため柔らかく、糸で切断出来たことが瓦に残る切断面から推測されているが、どんな材質の糸を使ったのかは分かっていない。現在小林さんのところでは、鎌倉時代の焼成炉を復元し、33%の粘土から作った瓦を焼いてみようと計画している。今の水分量だと焼成時に10%程度の寸法収縮がある。
瓦の成型工程では、職人が中宮寺の獅子口瓦の成型をしていた。文化財や寺社の修理に使用される瓦の注文が入るが、修理用は一個とか二個とかの極小量注文であるため、型を起すことはせず一つ一つ手作りとなる。また瓦の欠けた部分のみの修復を依頼されることもあり、それらのサンプルが並んでいるのを見ると、非常に手間の掛かる仕事であることが理解出来た。古代瓦の複製が作れるようになるまでには、約10年の修行が必要となり、簡単なことではない。古代瓦といっても時代による差は大きく、鎌倉時代までは仕上げも大雑把で気にしていないが、室町時代からは仕上げも良くなってくる。
焼成炉はガス窯であり、生ガスを入れてカーボンを付着させる。空気が入らないように外気と遮断しているが、外気の侵入有無が窯の寿命の目安となる。昔の窯ではマツやヒノキの根をカーボン源としていた。鉄分が多いとカーボンが旨く付きにくいことがある。中国では、上部に水の貯めがある窯であれば、陶磁器ではなく瓦を焼く窯だと分かる。水は水蒸気として、窯に空気が入るのを防ぐ目的に使用した。
工場見学が終わった後に、小林会長は展示された国内最古の法興寺瓦など古代瓦を手に取り、それらの由来を説明された。また参加者は展示されている鬼瓦や軒瓦などその他の古代瓦を自由にじっくりと観察することが出来たが、外面の模様や鬼の表情などは実に多様で個性的であり、優れた古代工人の表現力を伺うことが出来た。その後で小林会長から「古代瓦に学ぶ千四百年前の工人の知恵と技術」と題する講演をいただいた。
現存する日本最古の瓦は、法興寺の1,350年前の瓦である。飛鳥時代に材木および瓦が渡来し、国内でも瓦が焼かれるようになった。当時の寺社跡からは、渡来ものと国産のもの双方が出土している。飛鳥時代、奈良時代には穴窯が使われ、その後は平窯となって鎌倉時代まで続いた。その後室町時代になって横型の窯が使われるようになった。瓦の品質は、飛鳥時代、奈良時代と時代を経るに従って向上したが、その後平安時代に低下し、鎌倉時代になって再び向上した。鎌倉時代の質向上に貢献したのが、東大寺の僧重源である。重源は軒瓦に出っ張りを作り、そこに軒の先端が引っ掛かることによって瓦が落ち難い工夫をしている。この技術はその後消えてしまった。重源は東大寺の復興に貢献した僧として著名であり、中国に三回渡航したり、帰国出来ないで九州に滞在していた中国人石工を集めて使ったり、東大寺復興の資金集めを行ったりと行動力に優れていた。室町時代には、橘三郎国重、吉重親子が瓦技術を再興している。
代々の瓦職人の家系を調べてみると、一代が25年続いている計算となり、技術が途中で絶えてしまうことも良く起こった。瓦がずり落ちることを防ぐため、瓦止めの釘を使用するが、最初は木が使用された。しかし、強度を持たせるために木の釘は太くなり、瓦に開ける穴も大きくなる。そのため、雨が漏りやすくなる。鉄は強度が大きく開ける穴は小さくて済むものの、高価であること、錆びると膨張するため、瓦を割ってしまうことがある。江戸時代には鉄の代わりに銅製の釘が使われた。
瓦の役割は屋根に漏らさないように雨を流すことであり、そのため瓦を三枚重ねる三枚重ね(三枚葺き)が採用された。三枚の瓦をタテに順にずらせ、重なった中央を一本の瓦止めで束ねたもので、こうすることにより、毛細現象で瓦の隙間を6~7センチ雨が逆に戻っても、屋根には直接雨は流れない工夫となっている。この三枚重ねは江戸時代までは同じ様式のものが流通していたが、江戸時代以降は様々な形式のものが出てきて、大名毎に異なることもあった。例えば、真ん中が凹んだ平瓦を横に敷き詰め、その隙間に筒を半分に切った形をした丸瓦を跨がせ、凹んだ部分を雨が流れるようにした工法などである。
飾り瓦には、棟飾瓦(通称鬼瓦)、軒丸瓦、軒平瓦などがあるが、棟飾瓦(通称鬼瓦)は城の鯱鉾や寺社の鴟尾として馴染みがある。飛鳥時代の飾りは蓮華文であり、鬼はかなり後になってから出てきたが、元々は招福の神が起源とされる。獣面文がどこからきたかは不明であるが、大宰府で18種類の文が見つかり、これが日本最古と思われる。鬼は鎌倉時代に、堂内に置かれていた四天王が外に出てきたものと思われる。1363年以降になってオンの字が刻まれていたのが鬼になり、当初は鬼面に仏印(字や飾り)が刻まれていた。
また近代になって瓦の使い方に混乱が見られるようになった。屋根のてっぺんの合わせ目のところに、雨の進入を防ぐために使われたのが鳥衾瓦である。鳥衾瓦と棟端瓦は機能上一体のものであったが、明治から大正期に面の丸いものが出現すると、鳥衾瓦は消失していった。また鯱瓦は元来軒の端にあったものだが、これが端から内側に下がった例も出てきた。元々城には鬼瓦は使われず、家紋が使われていたはずであったが、現在松元、松江、高知の各城には鬼瓦が使われており、江戸時代の修理の際に使われたのではないかと思われる。中国や朝鮮で鬼瓦は使用された例はない。
日本の鬼瓦は1220年頃までは型押しで作られていたが、1240年以降になると手作業で作られるようになった。
良い瓦の条件は、呼吸している瓦である。今の瓦は空隙率21%であるが、鎌倉時代の瓦は空隙率が33%ある。また土も焼き方もその土地で異なるので、その土地で作られた瓦を使用するのがベストである。例えば、暖かい地方で焼いた瓦を寒い地方で使用すると、冬季に凍害(水分の凍結による)で割れてしまう。強度を十分に持たせた水分率5%の規格瓦を東大寺の屋根瓦に使用したところ、結露を起して屋根に水漏れを起してしまった。また瓦が割れる現象があり調べたところ、良く焼けた完成瓦は割れ、半焼けの瓦は問題がなかった。原因は結露であり、良く焼けた瓦は結露を起しやすく、その結露で止め釘が錆びて膨張し、瓦を割ったことが判明した。古代瓦ではこのようなことは起きない。
次いで志村先生より、「古代瓦の製造プロセスと半導体結晶加工プロセス」について講演をいただいた。
2000年に薬師寺大講堂が落成したが、工事には73,600の屋根瓦が使われた。瓦の一枚一枚に焼かれた炉内位置の番号が振られ、それによって使用場所が決まることに対する驚きがあって古代瓦に興味を持った。古代瓦の製造法を調べてみると、鎌倉時代の柔らかい粘土から作られた瓦では、ワイヤーが粘土の切断に使用されていることが分かった。
半導体ではシリコン結晶インゴットの直径が増大したため、切断刃の撓み、削り屑のムダが問題となってきた。これに対応するため、切断に使用する刃が外周刃→内周刃→バンドソー、マルチバンドソー、マルチワイヤーソーへと進化した。40センチのインゴットでは、マルチワイアーソーによる切断方法が採用されたが、この方法は古代瓦で使用されていた切断方法と同一であった。
質疑応答では、古代瓦の製造方法についての質問が出された。平窯とダルマ窯では冷却速度が違い、ダルマ窯では短時間となる。そのため、生産性や品質に差が出る。平窯では2段程度しか積めないが、ダルマ窯では4段は積める。4段に積まれた瓦で、下部の2段は良く火が回って良品として使用出来るが、上部の2段は不良品としてハネられる。しかし、不良品も捨てられるわけではない。寺社や城には、付帯倉庫など品質が低く寿命が短い瓦でも問題ない建物があるので、不良品なりに使い道があり、全部が使用可能である。
 瓦製造の責任者は、瓦長、瓦大工、瓦師などと呼ばれてきた。小林さんは、文科省の指定で国内ただ一人の鬼師と呼ばれている。元々の日本の瓦は一枚一枚がそれぞれ右や左に捩れている。それらを組み合わせて全体を平らにし、かつ瓦がずり落ちないように葺くのが葺き師である。現代の瓦は大量生産で全部が平らに作られているので、こういう技能を持った職人はいなくなってしまった。日本の屋根瓦は、全体を見るとピシッと綺麗に揃っているが、中国や韓国の屋根は歪になっているとのコメントが参加者から出されたが、これを裏付けている。
瓦製造の責任者は、瓦長、瓦大工、瓦師などと呼ばれてきた。小林さんは、文科省の指定で国内ただ一人の鬼師と呼ばれている。元々の日本の瓦は一枚一枚がそれぞれ右や左に捩れている。それらを組み合わせて全体を平らにし、かつ瓦がずり落ちないように葺くのが葺き師である。現代の瓦は大量生産で全部が平らに作られているので、こういう技能を持った職人はいなくなってしまった。日本の屋根瓦は、全体を見るとピシッと綺麗に揃っているが、中国や韓国の屋根は歪になっているとのコメントが参加者から出されたが、これを裏付けている。
古代の職人がその土地の土や気候を知って、それに合わせたもの作りをした結果、1400年経っても使用に耐える瓦を作り出してきたことは、まさに先人の知恵であり、現代に生きる我々にとっても学ぶことが多い。それこそ志村先生のご指摘通り、「温故知新」である。古いから良いということではなく、良いものだけが結果として現代に生き残り、「古きもの」として存在していることを考えると、様々な現代技術社会の矛盾が噴出している今こそ、「古きもの」の存在意義に立ち返るべきではないかと思われてならない。(文責 相馬和彦)
- Newer: ナノテク大国の課題/丸山 瑛一 氏
- Older: クレハが挑む世界オンリーワンの技術開発