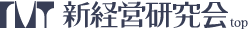- 2010-03-07 (日) 18:07
- 異業種・独自企業研究会
と き : 2009年11月12日
訪 問 先 : セイコーエプソン(株) 諏訪南事業所
講 師 : 代表取締役社長 碓井 稔氏
コーディネーター: 相馬和彦氏 (元帝人(株)取締役 研究部門長)
2009年度後期の第3回は、平成21年11月12日に、長野県諏訪市にあるセイコーエプソン本社および諏訪南事業所を訪れた。セイコーエプソンはインクジェットプリンターとデジタル腕時計で名をはせているが、グローバル規模で激変するビジネス環境を克服し今後の更なる発展を目指して、「長期ビジョンSE15」を最近設定した。今回の訪問では、経営トップの碓井社長より長期ビジョンの核心を直接お聴きすると共に、同社のコア技術の見学をお願いした。
最初に碓井稔代表取締役社長より、「セイコーエプソンの長期ビジョン[SE15]について」と題した講演をいただいた。セイコーエプソンの事業ルーツは、1942年創業のメカウオッチにあるが、1964年の東京オリンピックで使用された水晶クロノメーターとプリンティングタイマーの開発で更なる飛躍が出来た。事業基盤が出来たのは、1968年のミニプリンターと1969年のアナログクオーツウオッチのお陰で、このときは要素技術を自社開発し、それぞれの要素技術が事業へと発展した結果である。その後も要素技術の自社開発は企業文化として継続され、それがセイコーエプソンの強みであるが、同時に事業化という観点からは一定の限界にもなっているという反省がある。
事業規模はこの間に飛躍的に拡大し、1969年に100億円だった売上は、2008年時点で11,224億円に増加した。事業内容も、1969年はウオッチが100%であったが、2008年は情報関連機器が67%、電子デバイス27%、ウオッチ6%の比率となった。
現在の社会のトレンドを見ると、企業にとって重要な視点はグローバリティ、環境、ビジネスモデルであり、成長を捉えるチャンスと変化に遅れるリスクが共存している。
セイコーエプソンとしては、成長を捉える新たなチャンスとして、3つの道筋を考えている。
①強みが生かせる分野に集中する。
②集中する事業では、事業ベースを徹底的に強化する。
コストに向き合う。顧客志向を徹底する。
③保有する強い技術と販売資産を活用し、新しい製品と事業を生み出す。
長期ビジョン[SE15]を要約すると、「省・小・精のコア技術を極め、強い技術を束ねて
プラットフォーム化し、付加価値を加えて強い事業集合体となること」である。それによって、世界中の顧客に感動を与えることが出来る「なくてはならない会社」を目指す。特にプリンター、プロジェクター、水晶・センサーを三つの重点事業分野に設定し、この分野でのコア技術開発体制の強化と技術のプラットフォーム化を展開している。
①マイクロピエゾテクノロジー
セイコーエプソンのインクジェットは、マイクロピエゾ方式であり、この方式で実現可能な機器はすべて手掛ける方針である。特にビジネス用、産業用、商業用(ミニラボ用)に注力し、捺染用、カラーフィルター製造用プリンターなどの開発が行われている。
②3LCDプロジェクター
1988年に上市し、全プロジェクターの60%を占めている。今は文教用が主であるが、これをコンシューマー用、商業・産業用への展開を図る。
③水晶デバイス
水晶と省電力IC技術を組み合わせ、安心、安全、快適を生み出す新デバイスを開発中。例えば、高精度のジャイロセンサー、精度が±30paの絶対圧センサー(空気中で3cmの高度差を検出可能な精度)などがある。
特許出願にも力を入れていて、国内登録件数で7番、米国登録件数で14番の位置にあるが、これを事業という実績に結びつけたい。技術のタネは多いが、それをもっと具体的な製品や事業の創出へ結びつけたい。
次にグループに分かれてものづくり塾を見学した。ものづくり塾は、ものづくり歴史館と技能道場からなり、筆者のグループは、最初にものづくり歴史館、ついで技能道場を見学した。ものづくり歴史館にある製品の歴史・変遷の展示室は、技能・技術教育の一環として、1990年以降入社の新人には、0から1の発想の大切さや改善・改良の意味を考えさえる場として活用している。会社の歴史・デバイス展示および時計展示室を次に見学した。セイコーエプソンでは、部品まですべて自製する方針だったが、最近では部品の90%は外部から購入している。時計では自製率は70%を未だ維持しているとのことであった。技能道場ではものづくりの原点を教育するため、工作機械は全部マニュアルで揃え、単に技能を向上させるだけでなく、人づくりも目指している。技能五輪45種目中の3種目に挑戦している。技能道場への入門者は、希望者から選ぶ方式を取っている。
ものづくり塾の見学終了後、諏訪南工場へ移動し、「セイコーエプソンの研究開発体制」について、常務取締役 技術開発本部長の小口徹氏よりお話しを伺った。
技術開発本部のミッションは、新規事業創出、生産革新、技術課題可決の3つがある。新規事業創出は、コア技術を極めることにより、生産革新は生産技術を極めて生産性を向上させることにより、技術課題解決はKHを極めることにより達成を目指している。
平成21年4月にバリューチェーン事業体制が発足した。これは、従来は必ずしも旨く機能していたとは言えなかった、創る→作る→届けるという各プロセスを一体化することを目標にしている。そのために、知的財産本部、技術開発本部、事業部の3者が一体となって協力する体制が必要であった。
最後に業務執行役員 技術開発本部副本部長の福島米春氏より「エプソンの技術をお客様にお届けする商業・産業用向け機器の技術紹介」をいただいた後、展開中の最新機器を見学した。
①マイクロピエゾテクノロジー
駆動波形によって、用途別にインク制御を行う。具体的な機器としては、大型カラーフィルター、ラベル印刷機、捺染印刷機を見学した。大型カラーフィルターは2015年にアナログ印刷で33.3兆円、デジタル印刷で12.8兆円と予想されており、成長産業である。パネルの大型化に対応可能な機種を開発している。ラベル印刷機はフレキソを超える高画質で、一般のアナログ印刷用紙にも印刷可能である。ヘッドは2万ノズルあり、往復して印刷し全紙をカバーする。捺染印刷機はデザインの自由度が大きく、小ロットで短期の納入が可能で、低コストである。幅は1.8mまで印刷出来、インクは8色を使用している。欧州を中心に100台以上が販売されているが、厚地やベタ印刷には不向きである。
②3LCD
デジタル情報量が急激に増加しているので、これへの対応を行っている。超精密プロジェクターは3Dで4K(縦4K、横2K)、静止画像で8K(縦8K, 横4K)の処理が可能で、150インチのスクリーン画面では織物の細かい織り目まで見える。リアリティー感、質感が感じられ、車の設計、住宅の説明、バーチャル美術館、ファッションショー、劇場・映画館なでへの応用が候補となる。
③水晶デバイス
小型高精度圧力センサーは、圧力0.3paの変化が測定可能である。超小型原子発信器は従来よりもサイズが1/100、消費電力は1/100以下を達成した。300年で1秒の誤差という精度である。
見学がすべて終了した後で会場に戻り、ラップアップを実施した。近年の厳しい事業環境を反映し、どこの日本メーカーでも直面している課題に対する質問が多く出されたが、ほぼ全部について碓井社長が自ら回答された。要点のみ以下に纏めた。
①従来は部品まで全部自作していたが、最近は外部購入の割合が大きくなっている。そういう環境でコア技術の進化や新規コア技術の育成はどうやるのか?
→ コア技術と言っても、従来は事業の延長上のコア技術が中心だった。今後はそれだけでなく、新しいコア技術の構築を課題としている。新規事業を創出するコア技術については、タネまでは沢山作ったが、その事業化が必ずしも旨く行かなかった。技術開発だけでなく、事業の出口を見据えながらの開発を行おうとしている。事業部の延長ではない新事業を創出するため、事業部と技術開発本部からなる現体制に変更した。
②現在の環境を踏まえた開発対象は?
→ 開発の対象としては、商品そのものの開発、生産プロセスの開発、新しい産業構造に変えうる商品の開発、リサイクル技術開発がある。
③装置の外販についてはどういう方針か?
→ 今までは装置の外販には熱心ではなかったが、新方針として、装置を自社で最後まで作れる場合には外販することとし、自社で製造しないような商品を作るための装置は外部へ出した。
④セイコーエプソンの従業員は78,000人に達し、その内で海外従業員は50,000人も居るということだが、今回のような新方針を全社に徹底するためにどのような方策を取っているか?
→ 何度でも話すことに尽きる。社長自身が機会あるごとに話しているが、それぞれの立場にかみ砕いて話すことが重要で、これは事業部長の仕事の一つと位置づけている。
⑤最初のアイデアの創出は?
→ 過去も現在も、アイデアは沢山あったが、これを市場に出す力がイマイチだった。これからは仮説を立て、それを立証する行動が必要だ。
今回の訪問で、セイコーエプソンは創業以来コア技術の創出とそれをプラットフォームにした事業構築を企業文化としてきたことが、講演の内容および歴史館展示物から良く理解出来た。厳しい経済環境を、ものづくり企業としてどう乗り越えて更なる発展へ繋げるかという方針も、その企業文化を濃厚に反映したもので、同じ環境に直面しているメーカーには大きな示唆を与えている。特に所有しているコア技術に基づいたプラットフォームの上に事業を構築し、更に新しいコア技術を創出することによって新しいプラットフォームを作り上げ、その上に新規事業を創出しようという戦略は、ものづくり企業の王道であり、継続実施されれば必ず新規事業を創出するであろう。(文責 相馬和彦)
- Newer: 次世代ロボテイクスフロンティア・サイバニクスの開拓
- Older: 太陽光植物工場が挑むサイエンスとしての農業