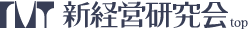Home > アーカイブ > 2012-02
2012-02
日本ゼオンが挑んだ高機能光学フィルム ゼオノアの開発/日本ゼオン 高岡工場
- 2012-02-15 (水)
- 異業種・独自企業研究会
《と き》2011年12月9日
《訪問先 》日本ゼオン(株) 高岡工場(富山県・高岡市)
《講 師 》取締役常務執行役員 荒川公平氏
《コーディネーター》テクノ・ビジョン代表、元帝人(株)取締役 研究部門長 相馬和彦氏

平成23年12月9日に、日本ゼオン(株)高岡工場を訪問した。高岡工場は、元々は塩ビの生産工場であったが、石油化学製品のグローバルな市場変化とコスト競争によって生産中止となり、高機能なゼオノア製フィルム工場に転換された。ナフサの熱分解で副成するシクロペンタジエンを原料とした樹脂およびフィルムは、ポリマー固有の優れた光学特性および低吸湿性により、光学レンズ・プリズム、LCD導光板、光学フィルムなど高機能材料として普及している。C5留分の有効利用から始まったプロジェクトが、新しい材料として市場に受け入れられるまでには、大変な努力とご苦労があったことは、素材開発に携わった技術者には容易に想像出来る。多くの障害を乗り越えるためには、何よりも強いリーダーシップが不可欠だったであろう。今回は、ゼオネックスフィルムの開発から事業化まで、実際にプロジェクトリーダーとして牽引された取締役常務執行役員の荒川公平氏から、事業化までの経緯と開発思想をお聞きすると共に、ゼオネックスフィルムの成膜工場の見学を含めた訪問となった。
最初に取締役常務執行役員 研究・知財担当の荒川公平氏による「日本ゼオンが挑んだ高機能ゼオノア製光学フィルムの開発」と題した講演を伺った。冒頭に触れたご自分の経歴では、日本ゼオンが3社目で、その前に日機装、富士フィルムに勤務していたことが紹介された。驚くことは、荒川氏がそれぞれの企業で新技術・新商品の開発に成功したばかりでなく、企業毎の代表的な技術・製品に成長させたことである。企業文化が異なる3企業のすべてにおいてこれだけの実績を上げることは、国内では希有の例であろう。また、リーダーシップと組織活性化への手腕が並大抵のレベルではないことも示している。事実、日本ゼオンにスカウトされた際には、これだけの人材の移籍実現にはかなりの波紋があったことが伺えた。
具体的な実績として、日機装(1978-1988)では気相法カーボンナノチューブ、富士フィルム(1988-2001)ではwide-viewフィルム、日本ゼオン(2001-現在)では、2002年に溶融押し出し延伸光学フィルム、2003年に視野角拡大フィルムの事業化に成功している。いずれの商品も、現在では各社の主力技術・商品となっている。このような高度な実績を実現するためには、その背後に独創的な開発思想と開発手法があるのは容易に想像され、それらに触れることが出来ると冒頭から大きな期待を抱いた。
日本ゼオンは1950年4月12日に設立され、2011年3月末時点の資本金242億円、連結売上2,704億円、連結営業利益353億円である。従業員は連結で2,836人。基盤事業であるエラストマー素材事業で、合成ゴム、合成ラテックス、化成品(石油樹脂、熱可塑性ゴム)を有し、新規展開を目指している高機能材料事業で、化学品(合成香料)、情報材料(電子材料、重合法トナー)、高機能樹脂(シクロオレフィンポリマー)、高機能部材(光学フィルム)、エネルギー関連材料(リチウム電池バインダー)、医療器材を展開している。その他には、RIM事業や一般用加工事業などがある。
事業所としては、国内に5工場(高岡、水島、徳山、米沢、川崎)、2事務所(大坂、名古屋)、総合開発センター(川崎)を有し、海外には欧州、北米、アジアなど世界16ヶ国に展開中である。
ナフサ熱分解で生成するC4留分およびC5留分の精度高い分離技術を開発し、分離したC5留分の有効利用から新規事業を展開した。C4留分の分離プロセスであるGPB法は、世界19ヶ国、49プラント向けに輸出され、世界のブタジエンの約50%はこの方法で分離されている。またC5留分の分離法であるGPI法は、世界シェア-がNo.1である。
ゼオン製品には、世界シェア-の高いものが多く、例を挙げると、自動車のエンジン周りに使用される耐油性特殊ゴム(ゼットポール)では、世界シェア-が約70%、合成香料としての青葉アルコールでは世界シェア-が70~80%である。エンジンルームに使用されるゴムでは、約40%がゼオン製である。
COP(cyclic olefin polymer)のゼオネックス、ゼオノアは光学特性、耐熱性、低吸湿性(吸湿性0.01%)を兼ね備えていて、他の樹脂にはない特徴が認められ、レンズなど光学用途に利用されている。この特性を活かせば、今後も従来のプラスチックにはない新領域が開拓出来るのではないかと期待している。特に光学フィルムは、携帯機器から大型液晶TV、更には有機ELを含む幅広いディスプレー用途への貢献が可能と考えている。
以上述べて来たように、日本ゼオンの特徴的な製品群を開発してきた背景には、それを支える基本理念があった。それは、「ニッチでも、日本ゼオンらしい得意分野で、人の真似をしない、人が真似の出来ない、地球に優しい独創的技術にもとづく世界一製品・事業を継続的に創出し、社会に貢献する」というものである。強調されているキーワードに下線を引いたが、一言で言うと「コア技術を活かした独創的製品を継続的に創出する」ことであろう。これは「言うは易く行うは難し」で、実現するための仕組みがカギになる。
この基本理念を具体化するため、以下のような方策を取っている。
- 人の真似をしない。→ 真似をすると儲からなく、結局失敗することになる。トップユーザーとロードマップを共有しながら、提案型を実施している。
- 人が真似を出来ない独創的技術に基づく事業。→ 他社への優位性を有し、他製品へ展開可能な汎用性を有するテクノロジー・プラットフォーム(TP
)を強化する。生産技術はブラック・ボックス化し、プラントメーカーに作らせる設備は、他社に売らない契約を結ぶなどで、他社に真似されない技術とする。 - スピード。→ 開発スピードが重要なので、すべて自分ではやらない。専門性の高い分野は、外から人を連れてくる。しかし、TPには拘る。
- 全員参加。→ PDCAで回し、コンカレント技術会議を持つ。
- 継続的に創出。→ 適材適所を行いつつ、パラダイムシフターを発掘する。
経営戦略と研究開発戦略の一体化を図るため、社長が毎月研究開発会議に出席し、朝から晩まで丸一日若い研究者の話を聞いている。力を入れるテーマは、即断・即決するので、若い研究者のモチベーションも強化されている。
このようなやり方は昔からあったのではなく、歴史的には技術者が信用されない風土があった。1993年に当時の中野社長が新事業の開発を重視し、社長ヒアリングを始めた。そこから出たCOPが事業的に成功し、技術者の信頼が向上した。
COPは1991年に上市されたが、樹脂売りで10年間は赤字事業であった。その中で、2001年4月に当時の山崎専務の決断で、加工事業への進出のため、フィルム工場の投資が決定した。当時は、光学用の厚みムラ精度を実現するためには、溶液キャスト法でないと無理だというのが常識であったが、コストおよび環境面から判断し、敢えて熔融押し出しによる光学フィルム製造に挑戦した。
2001年9月に山崎氏は荒川氏をリクルートし、荒川氏のリーダーシップの下で技術開発が開始された。高岡工場は2001年12月に完成したが、フィルムの技術開発は継続され、漸く2002年10月1日に上市に成功した。熔融押し出し法によるゼオノアフィルムが上市された結果、市場価格は従来の溶液キャストフィルムに対比して1/2以下に急落し、コスト面での有利性が証明出来た。
荒川氏が参加してから、上市までのほぼ一年間の経緯を要約すると以下のようになる。
2002年1月 光学製品研究所を設立。 部下20名。
2002年2月 東北大学大見教授に紹介される。
次世代ディスプレー用部材のコストを1/10にする目標。
2002年3月 国家予算153億円決定。 大見プロジェクト発足。
2002年4月 輝度向上フィルムが採用される。
VA用位相差フィルムは不採用。2003年9月に別途スタートとなる。
2002年7月 厚さムラ±2%を達成し、ユーザー評価を開始する。
達成のためには、3つのノウハウが必要であった。
9月に厚さムラは±1%に達し、現在では±0.5%を達成している。
2002年10月 1ロールが購入される。
2002年11月 他社製品にクレームが出て、突然10万㎡の注文が入り、損益分岐点を超えた。
2003年9月、部材に関する5者会議でVA用位相差フィルムを提案した時の内容は、①ディスプレー縁部分の光洩れ低減、②部材削減(6枚→4枚へ)、③ロールツーロールによるプロセス簡略化であり、これが認められた。成膜技術としては、如何にして縦横に均一な物性を有するフィルムを作るかがカギとなった。特に横延伸時のボーイングによるムラ低減に苦労した。技術の課題を解決する際には、モノマーからフィルムまで全行程を自社で実施していたことが大きな強みとなった。その結果、2001年から2006年まで、ほぼ毎年設備投資が続くことになった。ただ、2007年10月に完成した氷見市のフィルム第二工場では、その月のサブプライム問題のため、竣工したものの稼働ゼロとなってしまったこともあった。
 以上ゼオノアフィルムの特性を活かした二つの国家プロジェクトを述べたが、国家プロジェクトへはもう一つの提案がある。それは、液晶ディスプレーの表示性能を改善するために、液晶パネルへの入射光を増加させることである。具体的には、輝度向上フィルムを使用することにより、拡散板から液晶への入射光を4%から6%に向上出来る。そのためには、複数の要素技術開発が必要となる。現在市販品のない高△n液晶の開発技術や、広帯域化技術、多層押し出し技術、斜め延伸技術などの業界初の技術開発も必要となる。斜め延伸による位相差フィルムの開発では、技術的な目処が付きつつある。
以上ゼオノアフィルムの特性を活かした二つの国家プロジェクトを述べたが、国家プロジェクトへはもう一つの提案がある。それは、液晶ディスプレーの表示性能を改善するために、液晶パネルへの入射光を増加させることである。具体的には、輝度向上フィルムを使用することにより、拡散板から液晶への入射光を4%から6%に向上出来る。そのためには、複数の要素技術開発が必要となる。現在市販品のない高△n液晶の開発技術や、広帯域化技術、多層押し出し技術、斜め延伸技術などの業界初の技術開発も必要となる。斜め延伸による位相差フィルムの開発では、技術的な目処が付きつつある。
光学フィルム分野で様々なプロセスイノベーションを達成して来たが、今後はそれらを
強化・発展させ、更なる展開を図って行く。斜め延伸位相差フィルムの応用としては、モバイル用の円偏光VAモード、3Dテレビ用の1/4波長板(反射防止)、電子看板、有機ELディスプレー用途などを考えている。
荒川氏がイノベーションを継続的に達成して来た中で、新しい発想を妨げる最大の障害は「思い込み」であり、これを排除することが最も効果ありと感じている。歴史的にも、そんなことは出来ないと学者や知識人が断言したことの多くが実現しているのは良い例だ。
思い込みを排除するに最も有効なのは、デカルトが言っているように「疑う」ことである。上司が言ったから、ノーベル賞学者が言ったから信じるのではなく、常識を疑うことで新しい発想や発明が生まれてくる。
また、新規事業開発を成功させるために、必須の人として、3つの異なるレベルのリーダーが必要だと思っている。一人は、信念と情熱で創出する研究開発イノベーター、二人目は、人生を賭けて推進する革新的事業部長、三人目は身を賭して守る革新的経営幹部である。
荒川氏の講演は、ご自身が身を賭して実現してきた具体的な内容が詳細に述べられ、リーダーとしての理念が明確で、かつ情熱溢れるものであった。過去に勤務した2社を含め、3社のいずれでも新製品の開発・事業化に成功された理由が納得出来た。講演の最後で述べられた新規事業開発に必須の3人が揃っていることは、残念ながら組織内では中々望めないことである。そのような環境下では、誰かが他の二人の役割を引き受けたり、強く引っ張ったりしなければならないのが現実であろう。荒川氏は多分そのような役割も兼ねたのではないかと想像出来た。また、イノベーションの原動力となるそれまでの常識を「疑う」ことは、筆者も現在まで方針としてきたことでもあり、全面的に賛同出来る考え方である。
講演が詳細かつ多岐に渡り、後の工場見学が控えていたため、残念ながら質疑応答の時間が割けなかった。参加者には、ライトパーティーで個別に質問するようにお願いし、残念ながら講演はここで終了とした。ライトパーティーでは、期待通り多くの参加者が荒川氏を囲み、活発な意見交換がなされた。
工場見学に移る前、執行役員 高岡工場 藤澤浩工場長による説明があった。
- 高岡工場では塩ビを製造していたが、現在は廃業して工場跡を整地し、新事業用地と位置づけている。
- 敷地面積は17万㎡あり、氷見工場と合わせて2011年4月時点で822名が在籍。光学材料、高機能材料、メディカル、プラント、研究などの活動を行っている。
- 子会社の(株)オプティスが光学フィルムを富山工場(高岡工場の隣)と氷見工場で製造し、佐野工場で医療用などを製造している。会社設立は1990年4月、従業員は405名。
- 生産能力は、富山工場が無配向から延伸まで含めたフィルムとして、3,000万㎡/年、氷見工場は二軸延伸が6、000万㎡/年、斜め延伸が1、000万㎡/年ある。富山工場は3段延伸だが、氷見工場は原反→縦延伸→横延伸の連続延伸に改良した。
次いでバスに乗り、高岡工場内を通過してから氷見工場へ向かった。高岡工場では、特殊ゴム(Zポール)プラント、COP樹脂のパイロットプラント、塩ビ工場跡地、電子材料用ガスプラント、研究施設の脇を通過した。氷見工場ではグループに分かれて工場見学を実施した。
工場見学は2階の窓から下のプラントを見下ろす位置で、延伸工程を見ることが出来た。窓があまり大きくないこと、2階からで詳細が良く見えないことがあり、視野は限定された。延伸工程の能力は、1ライン1、000万㎡/年、クリーン度は1、000、検査はin-lineで膜厚、異物、光学特性などをモニターしている。
今回の訪問で最も印象的であったのは、常識では不可能と考えられた技術目標に向かい、全員参加で障害を克服して行った過程で示された研究開発および経営におけるリーダーシップ発揮とリスク許容である。熔融押し出しによる成膜法が未だ確立していない段階にも拘わらず、プラントへの投資を決断し、技術開発を研究開発リーダーにまかせる度量は、現代の企業では滅多に見られるものではない。また、研究開発リーダーの指揮下、技術者全員で力を合わせ、それに応えたのも見事と言うしかない。
しかし、日本ゼオンのこのような企業文化は、実は昔からあったわけではなく、近年になって特定の経営トップが意識して築き上げ、それから企業文化として伝承されたという説明は、重要な示唆を与えている。1800年代から今日まで、200年に渡って永続的発展を遂げた世界的企業の分析から、永続的発展を可能にする企業文化は、必ずしも創立時からあったものではなく、ある時代の経営者が意志を持って築いた文化が今日まで継承されてきたことが指摘されている(J.C.コリンズ、J.I.ポラス著「ビジョナリーカンパニー」)。別の視点から見れば、永続的発展を実現してきた企業が、特定の経営者によってものづくりの企業文化を失い、低迷状態に転落することも容易に起こりうることを意味している。日本ゼオンのように、世界一の製品や事業を生み出すための企業文化を築こうという強い意志を持ち、それを具体化しようとする経営者がどれだけ出現するかが、低迷する日本企業の再生のカギを握っていることを改めて強く認識した。(文責 相馬和彦)
Home > アーカイブ > 2012-02