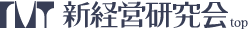- 2012-09-20 (木) 21:25
- 異業種・独自企業研究会
 2012年8月24日は、横浜市にある東洋製罐横浜工場を訪問した。東洋製罐は、金属缶やPETボトルなどの飲料・食品・生活家庭用パッケージの世界的メーカーとして知られている。飲料や食品の消費者として、缶・ボトルなどの包装容器に日常触れているものの、中味に対比して容器への関心度は必ずしも高くないのが現実である。近年の技術開発により、包装容器がガラスからスチール、アルミニウム、PETへと大きな変貌を遂げており、自動販売機とコンビニの普及と相まって、容器入りの飲料や食品による日常生活の利便性が格段に進歩した。その中心となって新商品を開発してきたのが東洋製罐であり、その優れた商品開発力の原点が何なのか、またどうやって継続的に新商品を開発してきたのかは、どの企業にとっても多大の関心がある。今回は横浜工場で、主力商品であるPETボトル、TULC缶、熔接缶などの生産ラインを見学し、新製品開発の歴史をお聞き出来ることを期待した訪問した。
2012年8月24日は、横浜市にある東洋製罐横浜工場を訪問した。東洋製罐は、金属缶やPETボトルなどの飲料・食品・生活家庭用パッケージの世界的メーカーとして知られている。飲料や食品の消費者として、缶・ボトルなどの包装容器に日常触れているものの、中味に対比して容器への関心度は必ずしも高くないのが現実である。近年の技術開発により、包装容器がガラスからスチール、アルミニウム、PETへと大きな変貌を遂げており、自動販売機とコンビニの普及と相まって、容器入りの飲料や食品による日常生活の利便性が格段に進歩した。その中心となって新商品を開発してきたのが東洋製罐であり、その優れた商品開発力の原点が何なのか、またどうやって継続的に新商品を開発してきたのかは、どの企業にとっても多大の関心がある。今回は横浜工場で、主力商品であるPETボトル、TULC缶、熔接缶などの生産ラインを見学し、新製品開発の歴史をお聞き出来ることを期待した訪問した。
最初に経営企画本部 経営企画部 佐藤一弘部長より会社概況が説明された。部品、機械、製品などの主要企業8社を核とした連結企業は57社あり、人員は7,000人、売上は7,300億円。製品別では包装関係が6,102億円、地域別では日本が6,424億円と国内中心である。
単体での売上は、3,251億円、人員は4,500人、国内に14工場を有している。容器の運搬は空気を運ぶようなもので、長距離の運搬はコスト的に不利なため、ユーザーの近くに工場を建てた。用途別では、飲料が69%、食品が18%、生活用品が8%等と、飲料用途が多い。容器の種類は、メタル、PET、フィルム(フレキシブル・パッケージ)などがある。海外生産は未だ低く、タイに集中しているが、中国へも進出した。
次いで、辻裕英横浜工場長より、横浜工場の概要説明を受けた。横浜工場は1963年に設立され、敷地は63,475㎡、従業員は365人いる。第一工場で金属缶を、第二工場でPETボトルを年間21億個生産している。東洋製罐が開発したTULC缶は、アルミやスチールのような従来缶に比べて大幅な改善となった。従来法を100%とすると、炭酸ガス発生量は84%に減少し、水は0%と全く使用しなくなり、かつ廃棄物は0.3%に減少した。
DVDによる横浜工場の概要説明があった後、工場見学に移った。
① 第二工場(PETボトル製造)
280㎤~2リットルのボトルを製造している。容量が小さくなると経済的に不利なので、どの程度の容量が現在では限界かと尋ねたところ、500㎤程度との返事であった
。これはPETボトルが米国で始めて市場に出た1978年に、筆者が独自に見積もった数字と一致したので、状況は当時と余り変わっていないと認識したが、後のパーティーで別の技術者に確認したところ、金型の改良によるプリフォーム数の増加(最大144個)等の技術進歩により、280㎤でも経済性が出るとのことであり、その後の技術進歩が確認出来た。
- プリフォーム成形工程 1回の射出成形で96~144個のプリフォーム成形が可能。
- 異物検査工程
- ノズル結晶化工程 高温充填の際に変形しないようノズルの部分を結晶化する。この工程の後一時保管し、次の工程にかけるプリフォームの温度を均一化させる。
- ブロー成形工程
- ボトル検査工程 見学時に計器に出ていたブロー成形工程での不良率は0.00032%と低い。全工程でも0.1%以下。
- パレット包装工程
② 第二工場(TULK缶製造)
- プレス工程 金属コイルからカッピングに成型する。
- 絞り工程 カッピングを3段階で筒状に絞る。
- トリミング工程 縁を切る。
- 印刷工程 凸版印刷で8色の印刷可能。各社毎の異なるデザインを印刷する場合には、母型を手動で交換する。切り換え時の印刷間違えを避けるため、検出機能プログラムを動かすこともある。
- 外面研磨工程
- 缶口絞り工程
 工場見学修了後、常務執行役員 テクニカル本部 伊藤譲二本部長のご挨拶をいただき、次いで執行役員 テクニカル本部 末俊雄副本部長による「東洋製罐の開発、包みの技術を基軸に、多様なニーズ・材料に挑む」と題した講演をお聴きした。
工場見学修了後、常務執行役員 テクニカル本部 伊藤譲二本部長のご挨拶をいただき、次いで執行役員 テクニカル本部 末俊雄副本部長による「東洋製罐の開発、包みの技術を基軸に、多様なニーズ・材料に挑む」と題した講演をお聴きした。
創設者高崎達之助の思想を反映したグローバル経営ビジョンは、「包みのテクノロジーを基軸として、人類の幸福・繁栄に貢献する先進テクノロジー企業をめざす」と制定していて、テクノロジー重視のものづくり企業としての姿勢が表現されている。
会社設立は1917年、国内14工場を有し、海外は容器生産で8社、アジアが中心であるが、包装材メーカーとしては、世界で売上第三位の地位を占めている。
PETボトルでは完全循環システムを採用しており、使用済みボトルから新ボトルに戻すため、PRT社でPETを分解し、DMT(Dimethyl Terephthalate)ではなくBHET(Bis-2-hydroxy Ethyl Terephthalate)に変換している。
包装材料以外の新事業として、ライフサイエンス(細胞培養など)、ナノテクノロジー、IT分野にも挑戦している。
 研究開発体制としては、ネットワーク活用を重視している。グループ内に総合研究所を有し、新コア技術の研究を行っている。ここの成果をテクニカル本部に移管して、実用技術開発を進めているが、テクニカル本部でも必要あれば基礎研究から始めることもある。総合研究所は1961年に設立され、グループ8社で運営している。包装容器や新事業のために研究を実施している。
研究開発体制としては、ネットワーク活用を重視している。グループ内に総合研究所を有し、新コア技術の研究を行っている。ここの成果をテクニカル本部に移管して、実用技術開発を進めているが、テクニカル本部でも必要あれば基礎研究から始めることもある。総合研究所は1961年に設立され、グループ8社で運営している。包装容器や新事業のために研究を実施している。
東洋食品研究所では、食の資源・科学・加工に関する研究を行っており、容器内容物の殺菌法なども研究対象となっている。2010年に公益法人化され、東洋食品短期大学が付属している。
テクニカル本部は1966年に発足したが、2012年に、それまでの容器分野別の組織が、技術分野別に改組された。7階建ての建物に入っているが、2階アネックスでは、顧客による充填・殺菌テストが実施されている。
東洋製罐では、包装容器は生産と消費の橋渡しが役割と位置づけられている。日本には包む文化があり、卵のつと、おひねりなど一種の民族文化となっている。
会社の歴史の中で、沢山の包装容器が開発・実用化されてきた。講演の中で数多くの開発技術・容器が説明されたが、ここではその中から極一部ではあるが、筆者の記憶に残ったもののみ記載した。
①TULC缶
1991年に上市し、その後進化・発展してきた。当初は内部に貼る延伸PETフィルムを購入していたが、無延伸フィルムを自社生産するようになった。絞り工程は当初3工程必要としたが、現在は1工程で可能。炭酸ガス発生量の減少、水の使用量ゼロ、廃棄物が0.3%に減少などの実績により、環境賞を2度受賞した。
軽量化では、熔接缶31グラム→TULC缶27グラム→TULC DC缶22グラム→TULC MIST缶18.2グラムと達成してきた。MIST缶は、陰圧缶でも打検(缶を叩いた音で欠陥を検出する検査法)が可能なように、微陽圧化したもの。
② TEC200
リシール可能なキャップ付きTULC缶。
③ 水無平板印刷
従来は凸版印刷で120線/インチで印刷していたものを、線数を大幅に増やし、しかも
水無平板で印刷が可能になった。ラベル缶には、グラビア印刷したフィルムを貼り付けている。エンボス缶では、陰圧缶ではキラキラ感を出し、陽圧缶では強度アップをしている。
④ プラスチックボトル
ボトルの開発は、バリア性をプラスチックにどう付与するかの技術開発史である。新製品として、検便、喀痰検査用の検査容器がある。技術開発例としては、複数の樹脂が境界部分で重なるように厚み変化をさせることで、容器色のグラディエーションが可能となった。PETにハイバリアー蒸着し、酸素、炭酸ガスの透過性を低下させた。オキシブロックでは、酸素吸収剤を利用し、熱いお茶の色が酸素で黒ずむことを防止している。圧縮成形法で、品質のバラツキの少ない工法を見いだした。取って付きのPETボトルでは、1.8リットル入りで10グラムの軽量化に成功した。
⑤ カップフレキシブルパッケージ
オキシガードカップ レトルトをホット状態で置いても、酸素による影響が少ない。
レトルトパウチ 電子レンジ対応のパッケージで、アルミ箔は使用せず、自動蒸気抜き孔が開いている。
⑥ 充填・殺菌技術
酸素を入れない充填、アセプテック充填、NS充填(殺菌剤を使用しない加熱殺菌が可能)、自己陽圧化機能付与などの技術を開発した。
今回の訪問で、今まで飲料・食品の中味にばかり気を取られ、うっかり見過ごしてきた包装容器には、様々な先端技術や工夫がなされており、世界のトップスリー企業の一員として、東洋製罐が新製品開発の先頭を走って来たことが良く理解出来た。その背景には、創業者の志が企業のビジョンに反映され、それを技術開発で実現させようという経営者および技術者の強い意志があった。包装容器は、生産者と消費者を繋ぐ橋渡しであり、食品の味や安全性、耐久性を守るために必須の役割を果たして来た。運搬や貯蔵に便利な包装容器なしには、今日の消費文化はあり得なかったことを実感出来た。
包装は、古来日本では相手への心遣いを表現する手段として、大切に守られて来ており、包装が文化として定着している。東洋製罐はその文化を、飲料や食品の流通段階で、消費文化を支える技術として普及させて来た。これからのグローバル競争の中でも、その精神を継続発揮し、日本文化としての包装容器で、世界のリーディングカンパニーとしての存在感を期待することが出来た(文責 相馬和彦)。